「すべての経験には価値がある」—フォースタート大内代表が描く、障害と社会の新しい関係
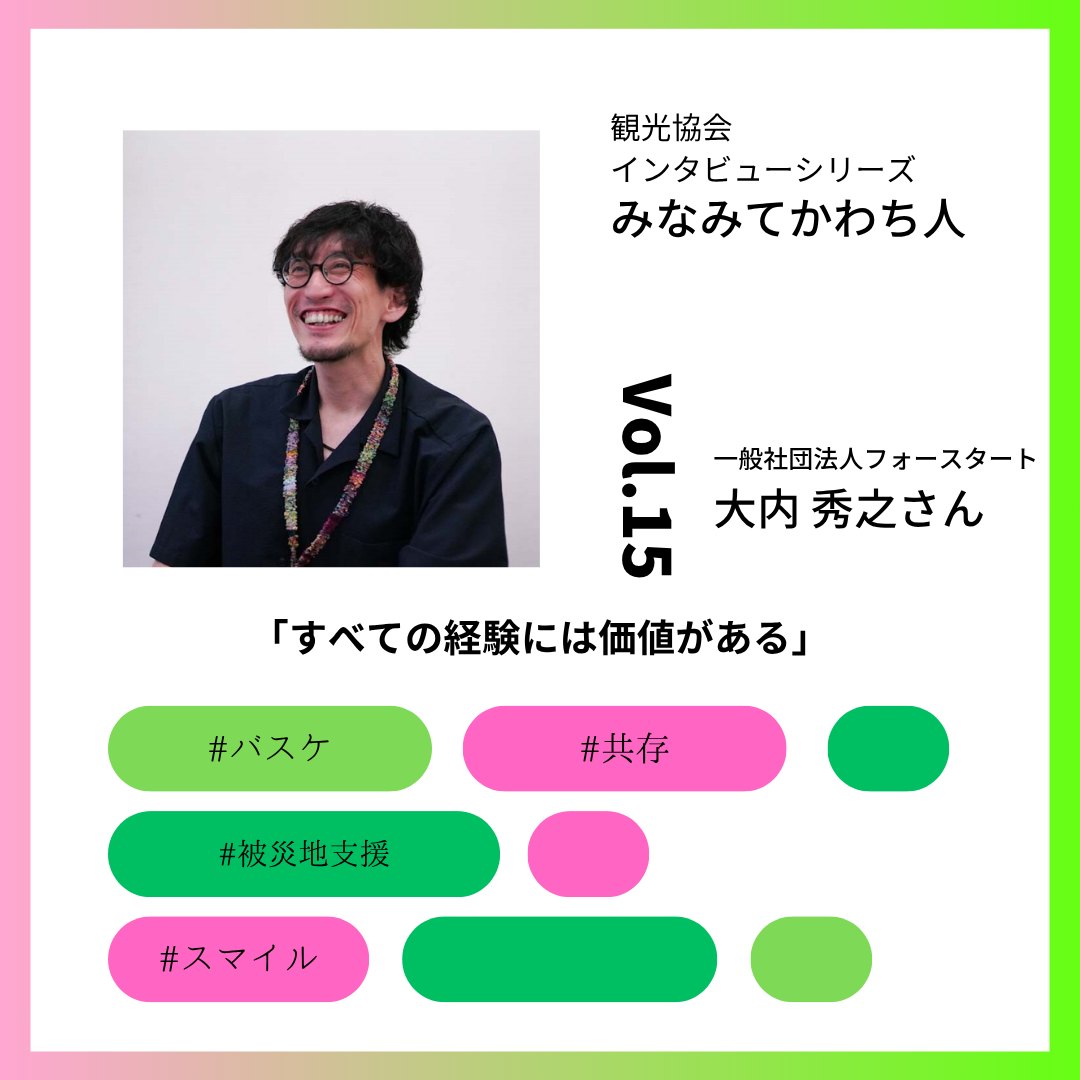
この度、松原や南河内地域で活動する方を取材する、「人」にフォーカスした特設ページを公開しました。
今回は松原を拠点に「障害のある人とない人が遊びを通じて共存していくキッカケの提供」を掲げる一般社団法人フォースタート(https://www.forcestart.info/)大内代表のインタビュー内容をお届けします。
幼少期の違和感と、車いすバスケとの出会い
兵庫県川西市で生まれた大内さんは、生まれつき小児がんによる足の障害を抱えていた。幼稚園からは障害のない子どもたちと同じ学校に通ったが、当時の社会はまだ「閉鎖的」。合理的配慮という言葉もなく、先生たちも試行錯誤を繰り返していた。
そんな中で転機となったのは、中学生のとき母に勧められた車いすバスケットボールとの出会いだ。最初は思うように体を動かせず、苦手意識ばかりが募った。しかし、ある試合で初めてシュートを決めた瞬間、心が震えた。
「そのときから車いすバスケにのめり込みました。障害の有無を超えて、同じルールで同じコートに立てる。僕にとっては初めて“対等”になれる場所だったんです」
学校教育とスポーツがつなぐもの
所属していたチーム「伊丹スーパーフェニックス」は、当時存続の危機に直面していた。車いすスポーツ自体がまだ珍しく、「障害者がスポーツを?」という冷ややかな目もあった。そんな状況の中で、大内さんは高校生ながらキャプテンを任され、地域の小学校に直接足を運び「授業で車いすバスケをやらせてください」と依頼した。
授業で車いすを操りながら笑顔を見せる姿に、子どもたちは大歓声をあげた。やがて彼らは練習に遊びに来るようになり、「チームメイト」として仲間入りしていった。
「障害のある人がビュンビュン動いていると、子どもたちの目が輝くんです。『好きな食べ物は何?』ってパーソナルな質問をしてくる。障害を超えて“人”として見てもらえるのが嬉しかった」
この体験を通じて「学校教育と障害者理解は親和性がある」と確信。10代の終わりには「いつかこれを仕事にしたい」という想いが芽生えていた。
福祉と経理、そしてフォースタートへ
大学では社会福祉士の資格を取得したが、当時は「障害のある福祉士はいらない」と言われることもあった。悔しさを抱えながらも、職業訓練校で経理を学び、大手企業に就職。数字を扱う仕事を通じて多くの人と出会い、視野を広げることができたが、心の奥底には「福祉に携わりたい」という想いが消えなかった。
その後、堺市立健康福祉プラザのオープニングスタッフに採用される。仕事終わりに練習できる環境を活かし、仲間を誘ってバスケットボールチームの「SAKAIsuns(サカイサンズ)」を立ち上げた。チームには障害の有無を問わずさまざまな人が集まり、地域に新しい風を吹き込んだ。
2018年、大内さんはついに一般社団法人「フォースタート」を設立。活動の目的はシンプルだ。
「障害者や被災者というラベルではなく、人と人として関わりたい。僕の目的は、人の笑顔をつくることです」

フォースタートの広がり——バスケとクライミング
フォースタートの活動は車いすバスケだけではない。クライミングや体験会など「遊びを通じた共存」をテーマに幅広い活動を展開している。
クライミングでは、障害の有無を問わず同じ壁に挑戦できる。ゴールをめざす瞬間は「障害者」「健常者」という境界線が消える。
「戦うのは自分の理想なんです。誰かと比べるのではなく、昨日の自分を超えられるか。それが大事なんです」
イベント参加者の中には「自分には無理」と思っていた人が、初めて登り切った瞬間に涙する姿もあったという。フォースタートは、ただのスポーツ団体ではなく、「一人ひとりが自分の可能性に気づく場所」として機能している。
災害支援で見えた「人と人のつながり」
フォースタートの活動は、災害支援にも広がる。大内さん自身、阪神淡路大震災を経験しているが、当時は「募金箱に小銭を入れるだけの自分が嫌だった」と語る。
2016年の熊本地震では、報道が減っていく中で「何かしなければ」と友人と現地へ。瓦礫に埋もれた町で出会ったおばあちゃんからかけられた「きいつけて帰りや」という言葉は、被災地での活動の原点になった。
能登半島地震でも同じだ。募金を集め、車で現地へ。倒壊した家屋が残る珠洲市で車いすバスケのイベントを開催した。「震災がなかったら絶対に出来ない経験でした」ある参加者から届いたメッセージは、大内さんの胸に強く刻まれている。
「被災地では、どうせもう来ないでしょと思われがちです。だからこそ何度も行く。人と人とのつながりを切らさないことが、僕の役割だと思っています」
実際、大内さんは能登に複数回足を運び、現地の高校生から「マブダチやもんな」と言われるまでの関係を築いた。
「平均点なんて、くそくらえ」
活動の根底にあるのは、自分自身を超えていく姿勢だ。
「僕は“平均点”には価値を置いていません。大事なのは、過去の自分を超えられるかどうか。だから『平均点なんてくそくらえ』って思っています」
この言葉は、障害の有無に関わらずすべての人へのメッセージだろう。
すべての経験に価値を
2025年11月、石川県立飯田高校で予定されている講演のテーマは「すべての経験は価値になる」。被災をネガティブに捉えるのではなく、「みんなは誰かのヒーローであってほしい」とメッセージを伝える予定だ。
「フォースタートがなくなる未来が理想です。わざわざ“障害者スポーツ”として教えに行かなくても、みんなが当たり前に一緒に楽しめる社会。それを目指したい」
すべての経験には価値がある。そう信じて、今日も大内さんは人と人を笑顔でつなげ続けている。

Writer
松原市観光協会・編集長 真本
