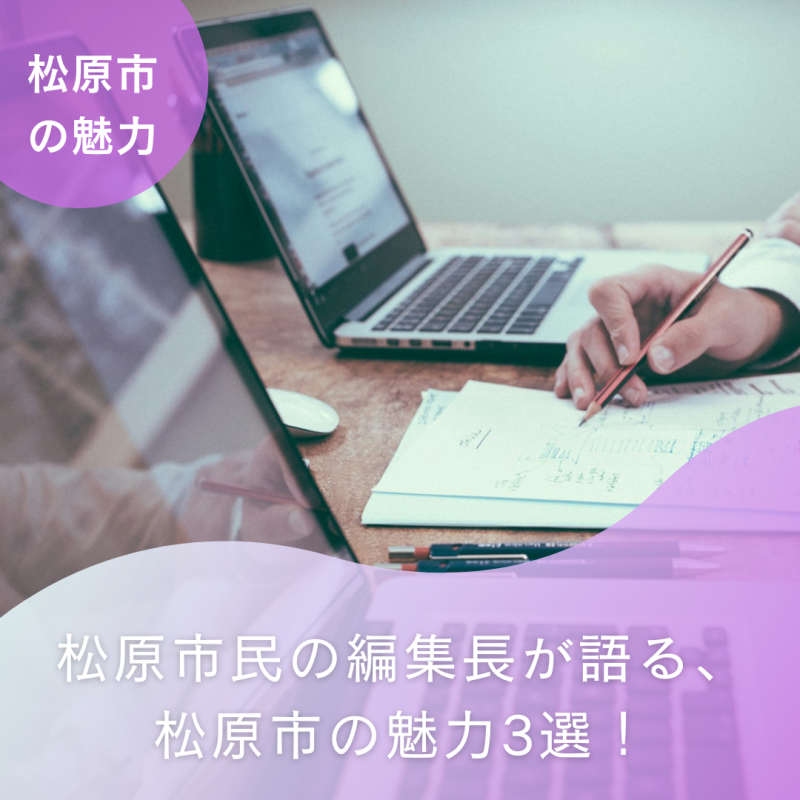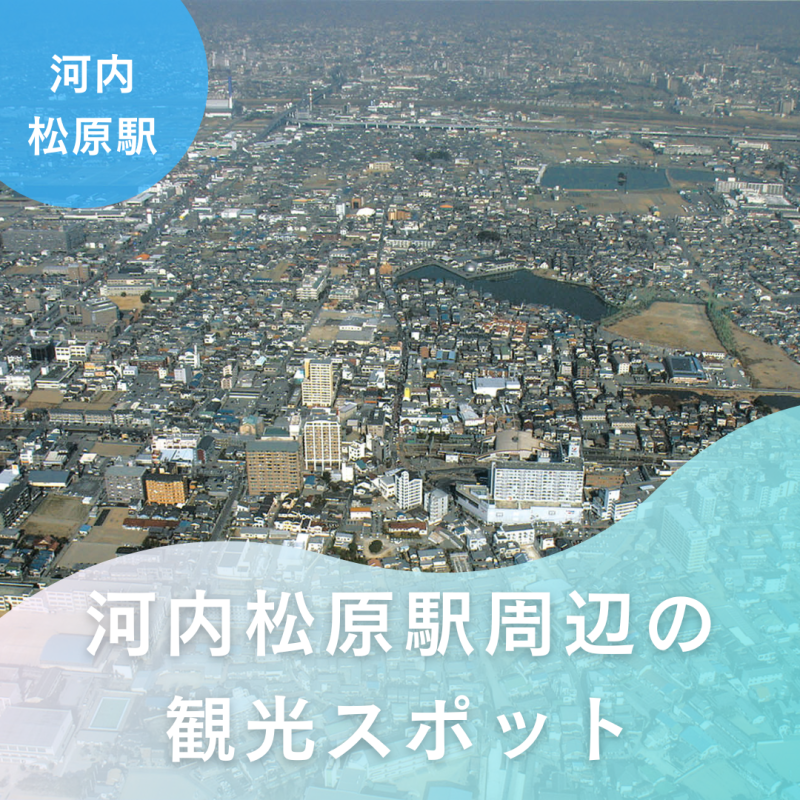松原の歴史はやわかり

この記事では、大阪府松原市の歴史について、ご紹介いたします。
南河内の玄関口
松原市一帯は南河内の入り口に位置しています。人の行き来を今に伝える竹内街道や中高野街道など古い街道が8本も残っており、街道の町という名にふさわしいエリアです。この一帯は古くは弥生時代以前から人の暮らしがありましたので、農耕生活の跡が上田町遺跡や河合遺跡などに残されています。

1989年に選定された「大阪みどりの100選」は、かつて大阪で開催された花と緑の博覧会を記念して一般公募で選出された、大阪府内の自然景観の名所です。この中には松原市からも、河内大塚山古墳の一帯が名を連ねています。
河内大塚山古墳は古墳時代の代表的な遺跡です。これは日本全国でも5番目に大きな巨大前方後円墳で、六世紀中ごろに造られたといわれています。鎌倉時代にはこの地の豪族丹下氏が墳丘内に丹下城を築き、江戸時代には古墳内に大塚村の村落が形成されました。

かつて都があったまち
歴史的には5世紀頃、都が置かれた時期がありました。「丹比柴籬宮」(たじひしばがきのみや)との名前が伝わっており、第18代の反正天皇が治世し、場所は松原市上田の付近とされ、現在その跡地にあるのが柴籬(しばがき)神社とされています。

地理的には難波から飛鳥へ行くための交通の要所として、多くの人が行きかう土地でした。
そのため、この地は進んだ大陸文化をいち早く取り入れることができ、文化の高い地域となっていました。
江戸時代にはたびたび氾濫する大和川の水害を防ぐために、大規模なつけ替え工事が行われ、新大和川が造られました。
明治時代になると町村制が発布され、この地域にはいくつもの村が誕生しました。松原村、天美村、布忍村、恵我村、三宅村などです。そして昭和30年の町村合併促進法によって、松原市が誕生しました。
Writer
松原市観光協会
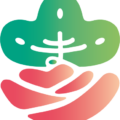
松原市観光協会・編集チーム
松原市や南河内(松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)にはたくさんの魅力があります。それらの魅力をわかりやすく編集してお伝えしていきます。